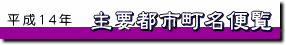 |
主要都市というと、都道府県庁所在地を思い浮かべるけれど、法的な定義からいえば、日本の首都である東京都を除いて「政令指定都市」がそれにあたる。
政令指定都市とは、地方自治法第12章第1節「大都市に関する特例」に規定され、政令により定められている市で、人口50万人(実態は100万人前後)以上を有し、都道府県が処理する事務の全部または一部を処理することができる行財政能力をもっている大都市のことをいう。
現在ある政令指定都市13市は、それぞれ旧市時代の成り立ちを比較してみても結構面白いことがわかる。
このページでは、それぞれの市を構成している「町名」だけに着目し、東京23区を含め、コツコツと比較研究してみることにした。きっと姓名判断のように、町名の名付け方に何か暗黙のルールがあって、個性的で独創的なルーツが見つけ出せるかも知れない。 |
|
|
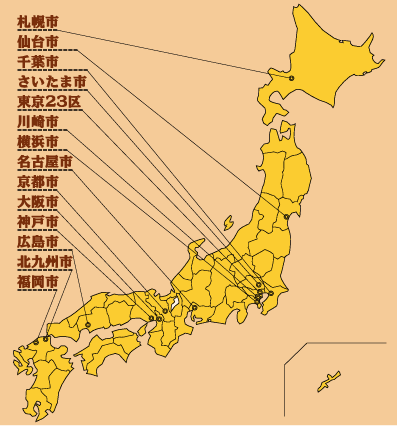 |
| 調べたい市をクリックしてください |
|
| ページを戻るときには、ブラウザの「戻る」ボタンをご利用ください。 |
明治22年4月市制町村制施行に伴い、特例法「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設ケル件」を制定。
しかし、これは複数区を束ねて特例市を形成させ、これまでの区の自治権を奪い、官選の府知事が市のトップとして職務をとり、府知事の下で区長が府の事務まで行うという制度だった。幾たびかに渡る反対運動で、明治31年10月廃止。
大正デモクラシー高揚の中、人口急増した大都市側から特別市制度創設運動が盛んとなり、東京・京都・大阪・名古屋・横浜・神戸に対し、大正11年3月に「大都市行政監督ニ関スル法律」が施行されたものの、戦時体制で形骸化、全国どの自治体も国家の統制下に入ってしまう。
戦後、5大市(東京市は、昭和18年に東京都に吸収されて消滅)は、大都市制度の確立に向けて運動を再開。昭和31年、地方自治法の改正(政令指定都市の制度化)により、京都・大阪・名古屋・横浜・神戸が政令指定都市に指定される。
以後、北九州(昭38)、札幌・川崎・福岡(昭47)、広島(昭55)、仙台(平1)、千葉(平4)、さいたま(平15)が指定された。
|
| 下表の都市名をクリックすると、公式ホームページへリンクします。 |
政 令 指 定 都 市
|
札幌 |
仙台 |
千葉 |
さいたま |
川崎 |
横浜 |
名古屋 |
京都 |
大阪 |
神戸 |
広島 |
北九州 |
福岡 |
人 口
(万人) |
184 |
102 |
91 |
105 |
129 |
352 |
219 |
146 |
262 |
150 |
113 |
100 |
137 |
面 積
(Km2) |
1121 |
788 |
272 |
168 |
144 |
437 |
326 |
610 |
221 |
549 |
741 |
485 |
340 |
| 行政区数 |
10 |
5 |
6 |
9 |
7 |
18 |
16 |
11 |
24 |
9 |
8 |
7 |
7 |
都道府県庁所在市(区)
|