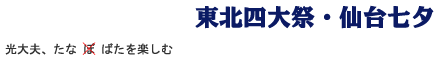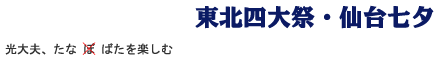|
|
| なぜか東北が好ましい。我れながら確固としたものではないし、年中行っているわけでもない。春から秋にかけて、ここへ行くとどんなだろうなぁ?と、地図やネットを眺めては、懐の深さに郷愁を覚えているにすぎない。特に杜の都・仙台へは、出かけることが多くなった。雑多さは否めないが、東北の中心都市だ。新幹線のおかげで思いのほか近いのがいい。 |
|
 |
 |
| 東北四大祭といえば、青森ねぶた祭(8/2〜7)、秋田竿灯祭(8/3〜6)、山形花笠祭(8/5〜7)、仙台七夕祭(8/6〜8)をいう。子供が小さい頃、よく平塚の七夕祭(7/7を基準に土・日曜日を含む4日間)に出かけた。平塚のは、新暦・梅雨時の七夕で青空天井の飾りだからビニール製なのが特徴。もともと戦後復興を祝う祭りとして、仙台の七夕祭を手本に開催されたものという。「平塚の七夕飾りをプラスして仙台の七夕が飾られる」とまことしやかに噂されたが、実際に仙台のを見てみると、すべて紙製。アーケードのある大きな商店街に飾られて雨の心配がないからだ。それも飾りの向こうにいる人が見えないほど、足下まで引きずるように飾られる。仙台の竹飾りは伝統的な決まり事があり、平塚のような驚く仕掛けはないが、紙の持つ風合いと質感を活かした色鮮やかな配色と細工が絢爛豪華だ。マイカーだと交通規制でシンドイよと忠告されたものの、さすが商都だけに駐車場の心配は無用だった。ただし昼間。平塚と違い露天商が極めて少ない。その分、普段飲食業に縁のない店が気合いを入れているものの、レストランなど混雑しているので計画的に行動しよう。 |
|
|
|
 |
| 仙台駅前はバスだらけ |
|
 |
| アーケードと人波 |
|
 |
| ドウモくんも登場 |
|
 |
| 記念撮影も余裕の広さ |
|
 |
| 変わり飾りもある |
|
 |
| NHK朝ドラ・ロケ地案内 |
|
|
 |
| 商店の稼ぎ時 |
|
 |
| 駅から一方通行の場合も |
|
 |
| こんな飾りもある |
|
 |
| アーケードの天井が高いわけだ |
|
 |
| 商店街の一角 |
|
 |
| 有名なお不動さん |
|
 |
| 仙台四郎グッズはここで |
|
| 伊達政宗公霊屋瑞鳳殿 寛永14年(1637年)に2代仙台藩主忠宗によって建立された政宗の廟所。桃山様式の豪華絢爛な建築物として国宝に指定されたが、昭和20年の空襲により焼失した。現在の門・本殿・資料館は、1979年に建てられたもの。ほかに、2代藩主忠宗、3代藩主綱宗の廟がある。資料館はコンパクトながら一見の価値がある。 |
|
|
|
 |
| 坂の勾配がきつい |
|
 |
| 霊屋とはいえ山の中 |
|
 |
| 拡大左 |
|
 |
| 拡大中 |
|
 |
| 拡大右 |
|
 |
| 殉死者の供養塔 |
|
 |
| 資料館内部 |
|
 |
| 2・3代藩主の廟 |
|
 |
| 2代忠宗・感仙殿 |
|
 |
| 3代綱宗・善応殿 |
|
 |
| 鹿児島県人七士の墓 |
|
|
|
| 周 辺 探 訪 |
| 仙台といえば、当然、松島に出かける。仙石線で約30分。松島海岸駅まで行って、瑞巌寺・五大堂を見て、遊覧船で塩釜に向かうというのがお決まりパターン。そこをあえて本塩釜駅で降り、鹽竈神社で参拝してから、浦霞酒造や御釜神社をぶらつき、マリンゲートから遊覧船に乗って松島へ。このほうが島々の見栄えもいいし、空席も多く余裕の船旅となる。七夕祭の時期、松島から塩釜へのルートはすべて満船状態になるので覚悟しておきたい。 |
|
 |
| 本塩釜駅 |
|
 |
| まぐろ付ポスト |
|
 |
| 塩釜 |
|
 |
| 狛犬あ |
|
 |
| 随身門 |
|
 |
| 狛犬うん |
|
 |
| 狛犬あ |
|
 |
| 左右宮拝殿 |
|
 |
| 狛犬うん |
|
 |
| 遊覧船 |
|
 |
| かもめの餌 |
|
 |
| 海に浮かぶ五大堂 |
|
 |
| 五大堂 |
|
 |
| 笹かまの実演販売 |
|
 |
| なぜか托鉢僧 |
|
 |
| 瑞巌寺岩窟 |
|
 |
| 瑞巌寺裏庭 |
|
|