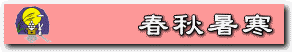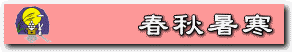|
 |
| 「はやぶさ」の後部には「さくら」が連結されている |
せめてテレビがないと時間を持て余してしまう客室 |
 |
 |
| 下関に到着するとカラフルに色分けされた列車が並んでいた |
 |
 |
| 新幹線に主要駅の座を奪われてノンビリが似合う駅 |
古くもなく新しくもなくこれといった特徴もない駅舎 |
 |
 |
| 駅前の「漁港食堂」は名前の割りにきれいな店。いわゆる「おふくろの味」で安く、一押しの食堂だ |
 |
 |
| 駅前ペデストリアンデッキにある「平家踊りの群像」 |
大歳神社の階段を見上げると上る気がしなかった |
 |
 |
| 大きな建物は関釜フェリーのターミナル |
今一番新しい「海響館」行きのサンデンバス |
 |
 |
| 唐戸は市役所もあって下関市のヘソ。「馬関」と呼ばれていたころの建物が並び、往時を偲ばせている |
 |
 |
| 店じまいに忙しい時間、唐戸市場をのぞく |
唐戸市場の前にある亀山神社。かなり大きい |
 |
 |
| 亀山神社から続く展望所。実は商店の屋上なのだ |
お亀さんの祠とイチョウの木 |
 |
 |
| 難病治癒に霊験ありという「お亀ぎんなん」200円。実のアバタが由来なのだが、これってどこにもあるの? |
 |
 |
| 亀山神社の参道横にある山陽道基点の石柱 |
床屋という名の由来がここにあるという記念碑 |
 |
 |
| 日清戦争後の講和条約締結地・春帆楼にある記念館 |
締結の様子を部屋や調度品で再現している |
 |
 |
| 清国全権・李鴻章が暴漢に襲われ、避難路となった道 |
音符の門が特徴的な藤原義江記念館(休みだった) |
 |
 |
| 李鴻章が宿舎として使った引接寺 |
引接寺山門の天井にある伝・左甚五郎彫刻の竜 |
 |
 |
| 竜宮を思わせる赤間神宮。電話ボックスにも門がある |
春帆楼と赤間神宮に挟まれて、安徳天皇の陵墓 |
 |
 |
| 壇ノ浦で滅亡した平家一門の七盛塚。背後は天皇陵 |
平家一門の墓の前に建つ、芳一堂。まるで伝承そのまま |
 |
 |
| 赤間神宮の脇参道奥の、中国から遷座した大連神社 |
大連神社の並びにある大東塾(終戦時自刃で有名)の碑 |
 |
 |
| 謡曲・碇潜や歌舞伎・碇知盛の舞台を思わせる |
小公園から壇ノ浦と関門大橋を望む |
 |
 |
| 桜山招魂社へ行く前に腹ごしらえ。「舞米亭」のクジラカツ定食は時価で、700円。このボリュームは安い |
 |
 |
| 桜山招魂社はいたって普通の神社。背後に回りこむと、靖国神社のルーツとなった招魂石柱がいくつも並んでいる |
 |
 |
| 忌宮神社前の商店街の一角にある維新発祥の碑 |
仲哀天皇の熊襲征伐の際、豊浦宮が置かれた |
 |
 |
| 仲哀天皇・神功皇后を祀る忌宮神社 |
新羅国の塵輪(鬼の顔のよう)の首を埋めて石で覆った |
 |
 |
| 明治の元勲・乃木希典を祀る乃木神社 |
乃木神社の境内地には復元した生家が建っている |
 |
 |
| 乃木少年は勤勉だったが、父親からよく訓話を受けた |
明治帝に殉死したときの刀の拓本。血糊が生々しい |
 |
 |
| 長府武家屋敷の面影を色濃く残す、古江小路 |
代々藩中医家随一。武家より少し大きい菅家長屋門 |
 |
 |
| 鎌倉期禅宗様式が美しい国宝・功山寺仏殿 |
功山寺の歴史は室町まで遡る。長府毛利家の墓 |
 |
 |
| 守護大名・大内義長はこの寺の仏殿で自刃した |
長門攘夷堂(長府博物館)の脇にある万骨塔 |
 |
 |
| 幕末・馬関戦争の火蓋を切った砲台(レプリカ) |
早鞆の瀬戸ともいう。海にまつわる歴史に事欠かない |
 |
 |
| 下関から門司まで続く人道トンネル。780mにわたる道を利用する人は、そのほとんどが体力づくりのため |
 |
 |
| 救命胴衣は定員の一割常備。行き交う船舶の間をミズスマシのように走り抜ける。スリルと度胸の5分間だ |